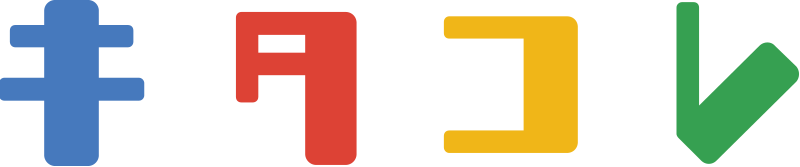(このページはアフィリエイト広告を利用しています)
モバイル保険は「複数デバイス所有者」の最適解。月額700円で3台まで守る圧倒的コストパフォーマンス
さくら少額短期保険株式会社が提供する「モバイル保険」は、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンといった複数の通信機器を所有・活用することが常識となった現代のデジタルライフスタイルにおいて、最も合理的かつコストパフォーマンスに優れた防衛策です。
この結論に至る理由は、モバイル保険が持つ以下の4つの核心的価値に集約されます。
- 圧倒的なコストパフォーマンス:
月額わずか700円(非課税)という固定料金で、最大3台のデバイスを同時に保護できる経済合理性は、他の追随を許しません 。 - 幅広い補償範囲:
日常生活で起こりうる「外部破損(画面割れなど)」「水濡れによる全損」「自然故障(メーカー保証切れ後)」「盗難」といった主要なリスクを包括的にカバーします 。
- ユーザー本位の柔軟性:
「中古端末OK」「購入後いつでも加入OK」「キャリアを乗り換えても継続OK」という、大手キャリアやメーカーの厳格な加入条件の「縛り」からユーザーを解放する、極めて高い自由度を誇ります 。
- 安心の自己負担0円:
修理時にユーザーが追加で支払う金額(免責金額)が一切ないため、万が一の事故の際にも突発的な出費を心配する必要がありません 。
モバイル保険の真の価値は、単なる「スマートフォンの保険」という枠組みを超え、個人の「デジタル資産全体」を包括的に、かつ低コストで管理できる点にあります。スマートフォン1台に1つの保険をかけるという旧来のモデルでは、現代のユーザーが直面するリスクを効率的にカバーすることは困難です。モバイル保険は、この「複数デバイス所有」という現実的な課題(ペインポイント)に対し、「1契約3台・月額700円」という非常に明快なソリューションを提供しているのです。
以下に、モバイル保険の基本スペックをまとめます。

引用:モバイル保険
| 項目 | 詳細 |
| 月額料金 | 700円(非課税) |
| 補償台数 | 最大3台(主端末1台+副端末2台) |
| 年間補償上限額 | 通算最大100,000円 |
| 自己負担金 | 0円 |
| 補償対象 | 外部破損、水濡れ全損、故障、盗難、修理不能 |
| 加入条件 | 新品・中古問わず、購入後いつでも加入可能 |
| 提供会社 | さくら少額短期保険株式会社 |
この記事では、これらの特徴を深掘りし、他社サービスとの徹底比較を通じて、モバイル保険がなぜ多くのユーザーにとって最適解となり得るのかを、2025年の最新情報に基づき専門家の視点から詳細に解説していきます。
2025年最新情報:モバイル保険のサービス全貌
モバイル保険のサービス内容を構成要素ごとに分解し、その詳細と専門的な視点からの意義を掘り下げます。
2.1. 料金プランと補償対象デバイス:月額700円の「包括的」な守り
モバイル保険の料金体系は、驚くほどシンプルです。月額700円(非課税)の単一プランのみで、追加オプションや端末価格に応じた料金変動は一切ありません 。この明瞭さは、利用者が長期的な予算を立てやすいという大きなメリットをもたらします。
この月額700円で、最大3台のデバイスを補償対象として登録できます。このシステムは「主端末」1台と「副端末」2台という構成になっており、それぞれの補償上限額が異なります。
- 主端末 (1台): 年間最大100,000円まで補償
- 副端末 (2台): 2台合計で年間最大30,000円まで補償
重要なのは、この主端末と副端末の指定はマイページからいつでも変更可能であるという点です。
例えば、新たに高価なスマートフォンを購入した際には、それを主端末に設定し、それまで主端末だった機種を副端末に切り替えるといった柔軟な運用が可能です。これにより、自身の所有デバイスの価値に応じてリスク管理を動的に最適化できます。
補償対象となるデバイスの範囲も非常に広く、「Wi-FiやBluetoothに接続可能な通信機器」が原則として対象となります。具体的には、以下のような多岐にわたるデバイスが登録可能です。
- スマートフォン(iPhone, Androidなど全キャリア・SIMフリー対応)
- タブレット(iPad, Androidタブレットなど)
- ノートパソコン(Windows, Macなど)
- スマートウォッチ(Apple Watch, Google Pixel Watchなど)
- ワイヤレスイヤホン(AirPods, Sony WFシリーズなど)
- 携帯ゲーム機(Nintendo Switch, PlayStation Portalなど)
- モバイルWi-Fiルーター
- デジタルオーディオプレーヤー(iPod touchなど)
この網羅性により、ユーザーはスマートフォンだけでなく、日常生活に欠かせない様々なガジェットを一つの契約でまとめて保護することができるのです 。
2.2. 補償内容の詳細:4つのリスクと「対象外」の境界線
モバイル保険は、日常生活で遭遇しうるデバイスの主要なトラブルを幅広くカバーしています。補償される事故は、主に以下の4つに分類されます 。
- 外部破損:
「スマートフォンを落として画面が割れた」「机の角にぶつけてカメラレンズが破損した」など、偶然の事故による物理的な損傷が対象です。 - 水濡れ全損:
「トイレに水没させてしまった」「飲み物をこぼして電源が入らなくなった」など、液体による故障が対象となります。 - 自然故障:
メーカー保証期間(通常1年)が終了した後に、ユーザーの過失なく内部的な要因で発生した故障(「突然電源が入らなくなった」「タッチパネルが反応しなくなった」など)をカバーします。 - 盗難:
外出先でカバンごと盗まれるなど、第三者による窃取が対象です。この場合、警察への盗難届の提出と受理番号の取得が保険金請求の必須条件となります。
さらに、修理が物理的に不可能な「修理不能」と判断された場合にも、見舞金制度が用意されています。この場合、主端末は最大25,000円、副端末は最大7,500円の見舞金が支払われます。これは、修理を前提としないユーザーにとっても一定の救済措置となる重要なポイントです。
一方で、ユーザーの誤解を招かないよう、補償されないケースを明確に理解しておくことが不可欠です。
- 「紛失・置き忘れ」は対象外:
盗難とは異なり、単なる不注意でどこかに置き忘れたり、落として失くしたりした場合は補償されません。これはモバイル保険の最も注意すべき点の一つです。 - バッテリーの経年劣化:
使用に伴うバッテリーの自然な消耗や性能低下は補償の対象外です。 - 外観上の軽微な損害:
機能に直接影響しない、すり傷、汚れ、塗装の剥がれといった外観上のダメージはカバーされません。 - ソフトウェア関連の不具合:
OSのバグやアプリのフリーズ、ウイルス感染といったソフトウェア上の問題や、それに伴うデータ復旧費用は補償対象外です。あくまでハードウェアの物理的な損害に対する保険となります。
2.3. 補償金額と自己負担金の詳細分析:年間10万円・自己負担0円の価値
モバイル保険の金銭的なメリットを理解する上で、補償上限額と自己負担金の2つの要素は極めて重要です。
年間補償上限額は、1契約あたり通算で100,000円に設定されています 。この上限額は、主端末と副端末で以下のように配分されます。
- 主端末1台で最大100,000円まで利用
- 副端末2台の合計で最大30,000円まで利用(例:副端末Aで20,000円、副端末Bで10,000円)
- 主端末で70,000円、副端末で30,000円といった組み合わせも可能
この上限額は1年ごとにリセットされるため、範囲内であれば年に何度でも保険金を請求できるという大きな利点があります。例えば、主端末の画面修理で50,000円の補償を受けた後、同じ年内に副端末のタブレットが故障して20,000円の修理費がかかった場合でも、両方とも補償を受けることが可能です。
そして、モバイル保険の最大の魅力とも言えるのが「自己負担金0円」という点です 。多くのスマホ保険では、修理や交換の際に「免責金額」として数千円から1万円以上の自己負担が発生します。例えば、American Expressの付帯保険では5,000円 、JCBの付帯保険では10,000円 、ワランティ少額短期保険の「スマホケ」でも5,000円の自己負担が必要です 。
これに対し、モバイル保険では修理にかかった費用が全額(上限額の範囲内で)保険金として支払われるため、利用者は急な出費を一切心配する必要がありません。月額料金の安さに加え、この自己負担ゼロの仕組みが、実質的な金銭的価値を飛躍的に高めているのです。
2.4. 加入条件と手続きの完全ガイド:誰でも、いつでも、オンラインで
大手キャリアやメーカーの補償サービスが「新品購入時のみ」といった厳しい加入条件を設けているのに対し、モバイル保険はユーザーにとっての門戸を広く開いています。
- 端末の条件:
新品・中古を問いません。フリマサイトや中古ショップで購入した端末でも加入可能です 。
- 加入タイミング:
端末購入時である必要はなく、いつでも好きなタイミングで加入できます。ただし、加入対象は購入から1年未満の端末(またはメーカー発売から5年未満)とされています(※最新の条件は公式サイトで要確認)。 - キャリアの条件:
ドコモ、au、ソフトバンクといった大手キャリアはもちろん、ahamoやpovo、LINEMO、その他格安SIM(MVNO)を利用している端末でも問題なく加入できます。キャリアの乗り換えを検討しているユーザーにとって、保険が継続できる点は大きな安心材料です。
申し込みプロセスは、すべてオンラインで完結する手軽さが特徴です 。
- 公式サイトにアクセス:
PCまたはスマートフォンからモバイル保険の公式サイトにアクセスします。 - 情報入力:
氏名、住所などの個人情報、支払い用のクレジットカード情報を入力します。 - 端末情報登録:
補償を受けたい端末の情報を登録します。特に、端末を個別に識別するためのIMEI(製造番号)の入力が必須です。IMEIはスマートフォンの設定画面や、電話アプリで「*#06#」と入力することで確認できます。 - 端末の写真アップロード:
申し込み時点で端末が正常であり、破損がないことを証明するために、端末の写真をアップロードします。画面が点灯し、IMEIが表示されている状態の前面写真と、背面の写真など、指定された写真を撮影して提出します。 - 申し込み完了:
全ての手続きが完了すると、登録したメールアドレスに受付完了の通知が届き、審査を経て契約成立となります。
モバイル保険の評判と口コミ:利用者のリアルな声から見る光と影
サービスの真価を測るためには、実際の利用者の声に耳を傾けることが不可欠です。SNSやレビューサイトから収集した評判を分析し、モバイル保険の「光」と「影」の両側面を客観的に評価します。
3.1. ポジティブな評価:「神コスパ」「請求が早くて助かった」
利用者から最も多く寄せられるのは、その圧倒的なコストパフォーマンスに対する称賛の声です。
- コストパフォーマンスへの絶賛:
「スマホ、タブレット、イヤホンの3台を月700円でカバーできるのは破格」「夫婦と子供のスマホを一つの契約にまとめて家計の固定費が大幅に削減できた」など、特に複数のデバイスを所有するユーザーや家族での利用者から高い評価を得ています。 - 迅速で簡単な保険金支払い:
「Webのマイページから申請するだけで、1週間もかからずに入金された」「店舗に行く必要がなく、すべての手続きがオンラインで完結するのが忙しい身にはありがたい」といった、請求プロセスのスムーズさと利便性を評価する声も多数見られます 。
- 精神的な安心感:
「中古で買った高価なiPhoneにも保険をかけられたので、安心して使える」「格安SIMに乗り換える際、キャリアの補償が切れる不安があったが、モバイル保険があったので迷わず移行できた」など、サービスの柔軟性がもたらす精神的なメリットを挙げるユーザーも少なくありません。
3.2. 注意すべき点とネガティブな評価:「立て替えがキツイ」「紛失はダメなのか…」
一方で、ネガティブな評価や注意喚起の声も存在します。ただし、これらの多くはサービスの欠陥というよりも、加入前の認識不足、すなわち「ユーザーの期待値とのミスマッチ」に起因するケースがほとんどです。
モバイル保険は「低保険料・自己負担ゼロ」という魅力的なモデルを実現するために、補償範囲を物理的損害に限定し、請求プロセスを「事後精算(立て替え払い)」方式に設計しています。この構造を理解せずに加入すると、「思っていたサービスと違う」という不満につながる可能性があります。
- 修理費用の一次的な立て替え:
ネガティブな口コミとして最も多く指摘されるのがこの点です。iPhoneの画面修理など、高額な修理には5万円以上かかることも珍しくありません。モバイル保険では、この修理費用を一度ユーザー自身が全額支払い、後日保険金として受け取る形になります。そのため、「一時的とはいえ、数万円の出費は厳しい」と感じるユーザーにとっては、この立て替え払いが大きな負担となる可能性があります。 - 「紛失」は補償対象外という事実:
「盗難」(警察への届出が必須)と「紛失」(単なる置き忘れや不注意による喪失)は明確に区別されており、後者は補償の対象外です。この点を理解せず、「スマホを失くしたのに補償されない」と不満を持つケースが見受けられます。頻繁に物を失くしてしまう傾向があるユーザーは、後述するAppleCare+の盗難・紛失プランなど、紛失をカバーする別のサービスを検討する必要があります。 - 修理は正規店が推奨される点:
保険金の請求自体は、いわゆる「街の修理屋さん」のような非正規店での修理でも可能です。しかし、非正規店で一度修理を行うと、その後のメーカー保証や正規店でのサポートが受けられなくなるリスクが伴います。そのため、モバイル保険側も基本的にはメーカーや正規サービスプロバイダでの修理を推奨しており、この点が一部のユーザーにとっては不便に感じられる可能性があります。
これらの注意点は、モバイル保険が「フィットしないユーザー層」を定義するための重要な判断材料となります。自身の経済状況やライフスタイルと照らし合わせ、これらの点が許容範囲内であるかを見極めることが、後悔のない保険選びにつながります。
【徹底比較】モバイル保険 vs 主要スマホ補償サービス11選
モバイル保険の独自の立ち位置を明確にするため、市場に存在する主要な競合サービスと多角的な比較分析を行います。
4.1. 総合比較表:全12サービススペック一覧
以下の表は、2025年時点での主要なモバイル補償サービスを一覧にまとめたものです。各サービスの違いを一目で把握するための、本稿で最も重要な情報の一つです。
表:2025年版 主要モバイル補償サービス 徹底比較
| サービス名 | 提供元/分類 | 月額料金(税込) | 補償台数 | 年間補償上限 | 自己負担金(修理/交換) | 盗難・紛失補償 | 中古端末加入 | 特記事項 |
| モバイル保険 | 独立系 | 700円 (非課税) | 3台 | 100,000円 | 0円 | ◯ (盗難のみ) | ◯ | コスパ最強、複数台所有者の最適解 |
| ケータイ補償サービス | ドコモ | 363円~1,100円 | 1台 | 交換 | 5,500円~12,100円 | ◯ | × | ドコモユーザー限定、端末購入時のみ |
| 故障紛失サポート | au | 機種による | 1台 | 交換 | 3,300円~8,800円 | ◯ | × | auユーザー限定、端末購入時のみ |
| あんしん保証パック | ソフトバンク | 715円~1,980円 | 1台 | 修理/交換 | 0円~8,250円 | ◯ | × | ソフトバンクユーザー限定、端末購入時のみ |
| スマホ交換保証プラス | 楽天モバイル | 715円~1,100円 | 1台 | 交換 | 6,600円 | ◯ | × | 楽天モバイルユーザー限定、端末購入時のみ |
| AppleCare+ | メーカー | 1,180円~ | 1台 | 回数無制限 | 3,700円/12,900円 | 別プラン | × | Apple公式の高品質サポート、紛失は高額プラン |
| スマホケ | 独立系 | 100円~400円 | 1台 | 100,000円 | 5,000円 | ◯ (盗難のみ) | ◯ | 1台だけなら最安だが、フル補償だと割高感 |
| クロネコスマホもしも保険 | 独立系 | 200円~790円 | 1台 | 10万~40万円 | 0円~3,000円 | ◯ | ◯ | プランが豊富、ヤマトの回収サービスが特徴 |
| justInCaseスマホ保険 | 独立系 | 390円~ | 1台 | 5万~22万円 | なし | ◯ | ◯ | 利用頻度で保険料が変動、AI活用 |
| Amexスマホプロテクション | クレカ付帯 | カード年会費 | 1台 | 3万~15万円 | 5,000円 | ◯ (盗難のみ) | – | カード決済が条件、あくまで付帯サービス |
| JCBスマートフォン保険 | クレカ付帯 | カード年会費 | 1台 | 3万~10万円 | 10,000円 | ◯ (盗難のみ) | – | カード決済が条件、自己負担が高い |
| スマホの保険証 | 独立系 | 約200円~ | 1台 | – | – | ◯ | ◯ | ※2023年12月で新規申込停止中 |
4.2. vs 大手キャリア補償(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル):『自由』か『縛り』か
大手キャリアが提供する補償サービスは、端末購入と同時に加入することが前提であり、一度キャリアを乗り換えてしまうとその権利は失効します。これは、ユーザーを自社の経済圏(エコシステム)に留めておくための「ロックイン戦略」の一環です。料金も高価な端末ほど高くなる傾向にあり、月額1,000円を超えるケースも珍しくありません 。
これに対し、モバイル保険はキャリアの縛りから完全に解放されています。格安SIMへの乗り換えを検討しているユーザーや、中古端末を賢く利用して通信費を節約したいユーザーにとって、キャリアに依存しないモバイル保険の存在は、経済的な自由度を大きく高める強力な選択肢となります。
4.3. vs メーカー補償(AppleCare+):『コスト』か『プレミアム体験』か
Appleが提供するAppleCare+は、ジーニアスバーでの対面サポートや、故障時に代替機をすぐに送ってくれるエクスプレス交換サービスなど、質の高いプレミアムなユーザー体験が最大の魅力です 。しかし、その料金は高額で、補償対象は1台のみ。さらに、盗難や紛失までカバーするプランは、さらに高額な料金設定となっています。
例えば、iPhone、iPad、Apple Watchの3製品を所有しているユーザーが、それぞれにAppleCare+を契約した場合、月々の保険料は合計で3,000円を超えることもあります。一方で、モバイル保険であれば、これら3台を月額700円でまとめて保護できます。この差は年間で数万円にも及びます。「Apple公式の至れり尽くせりのサービス」よりも「合理的なコストでの安心」を重視するユーザーにとって、モバイル保険の優位性は明らかです。
4.4. vs 他の独立系保険(スマホケ、クロネコスマホもしも保険など):『包括性』か『特化性』か
独立系の保険会社も、それぞれ特色あるサービスを提供しています。
- スマホケ:
「月額100円から」というキャッチーな価格が魅力ですが、これは最低限の「自然故障」補償のみの場合です。画面割れなどの「破損」や「水濡れ」をオプションで追加していくと料金は300円、400円と上昇し、モバイル保険との価格差は縮まります。1台の端末を最低限のコストで守りたい、という特化したニーズには応えますが、包括的な安心を求める場合には割高感が出てきます 。 - クロネコスマホもしも保険:
補償内容と料金に応じて3つのプランから選べる柔軟性が特徴です。最上位のプロプランでは自己負担金が0円になりますが、月額料金はモバイル保険より高くなります。ヤマトグループが提供する独自の回収・修理代行サービスは、手続きの手間を省きたいユーザーにとって魅力的です 。
これらのサービスと比較したとき、モバイル保険は「3台まで・月額700円・自己負担0円」という、多くのユーザーにとって最もバランスの取れた「スイートスポット」を突いたパッケージングであると評価できます。
4.5. vs クレジットカード付帯保険(Amex、JCB):『主保険』か『補助保険』か
American ExpressやJCBの一部のカードには、スマートフォン保険が「無料」で付帯しており、一見すると非常に魅力的に映ります 。しかし、これらの保険の実態は、カード利用を促進するためのマーケティング特典としての側面が強く、主力の保険として頼るにはいくつかの重要な制約があります。
第一に、保険適用の絶対条件として「直近3ヶ月以上の通信料を当該カードで決済していること」が挙げられます 。これはユーザーをカードの経済圏に固定化させるための仕掛けであり、支払い方法の自由を奪います。
第二に、補償上限額が3万円~5万円程度に設定されているケースが多く、近年の高価なスマートフォンの修理費用を全額カバーできない可能性があります 。
第三に、自己負担額が5,000円から10,000円と高額に設定されているため、軽微な修理では保険を使うメリットがほとんどありません 。
結論として、クレジットカード付帯保険は「持っているなら万が一の際に役立つかもしれない」という補助的な位置づけに過ぎません。能動的に、そして確実に自身のデジタル資産を守りたいのであれば、モバイル保険のような専用保険への加入が不可欠です。
あなたに最適なのは?ケーススタディ別・推奨プラン診断
ここまでの分析を踏まえ、具体的なユーザー像(ペルソナ)を設定し、それぞれに最適な補償プランを診断します。
ケース1:ガジェット愛好家・複数デバイス所有者
- 状況:
スマートフォン(iPhone 15)、タブレット(iPad Air)、スマートウォッチ(Apple Watch)の3台を日常的に使用。 - 推奨プラン:
モバイル保険が最適解。 - 理由:
3台のデバイスを月額わずか700円でまとめて保護できるコストメリットは、他のどのサービスも提供できません。高価なiPhoneを主端末に設定すれば、最大10万円までの手厚い補償を受けられ、コストと安心のバランスが最も優れています。
ケース2:最新の高価なiPhone 1台を徹底的に守りたいユーザー
- 状況:
購入したばかりのiPhone 16 Pro Max(20万円超)を所有。落下破損だけでなく、紛失や盗難のリスクも非常に心配。 - 推奨プラン:
AppleCare+ 盗難・紛失プランを推奨。 - 理由:
モバイル保険は「紛失」をカバーしません。最高価格帯の端末を失うリスクは計り知れず、コストが高くとも紛失までカバーし、Apple公式の迅速な交換サービスを受けられるAppleCare+が、このケースでは最も合理的な選択となります。
ケース3:コスト最優先!最低限の画面割れだけ備えたいユーザー
- 状況:
2年前に中古で購入したAndroidスマートフォン1台のみを所有。高額な月額料金は払いたくないが、画面割れだけは心配。 - 推奨プラン:
スマホケ(故障+破損プラン/月200円)も選択肢。 - 理由:
所有デバイスが1台で、かつリスクを「画面割れ」に限定できるのであれば、月額200円という圧倒的な低価格は魅力的です。ただし、補償上限額や5,000円の自己負担金は許容できるか、事前に確認が必要です。

引用:スマホケ
ケース4:家族全員のスマホをまとめて安く管理したい世帯主
- 状況:
自身、配偶者、高校生の子供がそれぞれスマートフォンを所有(計3台)。キャリアはバラバラ。 - 推奨プラン:
モバイル保険が最適解。 - 理由:
契約者を世帯主一人にまとめ、家族の端末を副端末として登録することで、家計全体の通信関連固定費を劇的に削減できます。3人がそれぞれキャリアの補償に加入する場合と比較すると、年間で2万円以上の節約になる可能性もあります。
ケース5:対象のゴールドカードをメインで使っているユーザー
- 状況:
American Expressゴールド・プリファード・カードをメインカードとして利用しており、毎月のスマートフォン通信料もこのカードで支払っている。 - 推奨プラン:
まずは付帯保険の内容を確認し、それで十分か判断。 - 理由:
このカードには年間最大5万円(自己負担5,000円)のスマホ保険が付帯しています 。所有デバイスが1台で、この補償内容で十分と判断できるのであれば、追加費用なしで済むため最も経済的です。しかし、補償額に不安がある場合や、他のデバイスも保護したい場合には、主保険としてモバイル保険への加入を検討するのが賢明です。
モバイル保険の評判・口コミ
モバイル保険に加入するとなると、実際の評判や口コミが良いのかという点は気になるポイントではないでしょうか。ここでは、モバイル保険の加入者によるX (旧:Twitter)でのリアルな口コミ・評判を集めてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。
モバイル保険は料金が安い!
X (旧:Twitter)スマホよく壊す人は
— マーグナーーーーーム‼︎‼︎‼︎‼︎ (@morinoyousei19) January 4, 2021
モバイル保険超オヌヌメ
金額安いしし補償範囲広い
モバイル保険の加入者によるTwitterでの口コミや評判を調査すると、とにかく「料金が安い!」と点に魅力を感じるという声が多く挙がっていました。モバイル保険は、月額700円で年間最大10万円の補償を受けることが可能です。
他社で提供されている保険と比較しても、モバイル保険は圧倒的なコストパフォーマンスの高さが大きな魅力と言えるでしょう。
1契約で3台登録、10万円補償される!
モバイル保険、月額700円でモバイル端末3台までの保険になるからAppleCareよりお得感だな(回し者ではない)
— ヘウレーカ (@heure_ca) September 22, 2021X (旧:Twitter)スマホ本体の補償がほしいなら
— しげ┃30代パパ×Webライター (@Shige_tsk_) July 24, 2021
『モバイル保険』がオススメ!
・月額700円
・1契約で3台まで補償してくれる
・パソコンやワイヤレスイヤホンなども補償可能
・10万円まで補償
値段と補償のコスパがよすぎる!
スマホ画面を割ったことがあるひとや
子どもに持たせてるひとは
入っておくと安心ですね!
モバイル保険は、月額700円で1契約で3台の端末を登録できる上、年間最大10万円の補償を受けることができます。つまり、1契約で3端末ということは、1台あたり月額234円という安さで利用することが可能ということです。
申し込みから保険金請求までの完全フローチャート
実際にモバイル保険を利用する際の具体的な手続きの流れを、ステップ・バイ・ステップで解説します。
STEP 1:加入申し込み
- 公式サイトへアクセス:
PCまたはスマートフォンでモバイル保険の公式サイトを開きます。 - 情報入力:
画面の指示に従い、契約者情報、クレジットカード情報、補償したい端末の情報(メーカー、機種名、IMEIなど)を入力します。 - 写真アップロード:
申し込み時点で端末に傷や故障がないことを証明するため、指定されたアングル(例:IMEIを表示させた画面、端末の四隅など)で撮影した写真をアップロードします。 - 完了:
申し込みが完了すると、登録メールアドレスに通知が届きます。後日、審査完了の連絡をもって契約成立となります。
STEP 2:事故発生〜修理
- 事故発生:
スマートフォンを落下させて画面が破損してしまった。 - 修理依頼:
Apple Storeやメーカーの正規サービスプロバイダ、またはキャリアショップに修理を依頼します。 - 立て替え払い:
修理が完了したら、その場で修理費用を一時的に全額自己負担で支払います。 - 重要書類の受領:
支払いが完了したら、「修理内容がわかる報告書(作業完了報告書など)」と「支払った金額がわかる領収書」を必ず受け取り、保管します。これらは保険金請求に必須の書類です。
STEP 3:保険金請求
- マイページへログイン:
モバイル保険の公式サイトからマイページにログインします。 - 事故報告:
「保険金申請」メニューから、事故が発生した日時、場所、状況などを入力します。 - 書類アップロード:
STEP 2で受け取った「修理報告書」と「領収書」をスマートフォンなどで撮影し、その画像をアップロードします。 - 申請完了:
全ての情報を入力・アップロードしたら、申請ボタンを押して手続きは完了です。
STEP 4:審査〜入金
- 審査:
さくら少額短期保険株式会社にて、申請内容の審査が行われます。審査は通常、申請から最短2営業日で完了します 。 - 入金:
審査で承認されると、申請時に指定した銀行口座へ保険金が振り込まれます。入金までの期間は最短で5営業日です 。
モバイル保険に関するよくある質問(FAQ)
最後に、読者から寄せられるであろう疑問点について、Q&A形式で回答します。
- Q1. 登録している端末(主端末・副端末)は後から変更できますか?
- はい、マイページからいつでも自由に変更可能です。新しい端末を購入したり、譲渡したりした場合でも、柔軟に登録内容を更新できます。
- Q2. 保険金の請求回数に上限はありますか?
- 年間補償上限額である100,000円の範囲内であれば、請求回数に制限はありません。少額の修理を複数回行った場合でも、合計額が上限を超えなければすべて補償の対象となります。
- Q3. 海外旅行中の事故も補償の対象になりますか?
- はい、海外で発生した破損や盗難といった事故も補償の対象となります。ただし、保険金の請求対象となる修理は、日本国内の正規店などで行われたものに限られます。帰国後に修理・申請する形になります。
- Q4. 法人名義での契約は可能ですか?
- いいえ、モバイル保険は個人向けのサービスとなっており、法人名義での契約はできません。
- Q5. 「スマホ保険」と「スマホ保険証」は違うものですか?
- はい、これらは全く異なるものです。「スマホ保険」は、本記事で解説しているような、スマートフォンの破損や盗難といった物理的な損害を補償する物損保険のことです。一方、「スマホ保険証」とは、2025年9月頃から本格利用が開始される予定の、マイナンバーカードの健康保険証としての機能をスマートフォンに搭載する国の制度を指します 。両者を混同しないようご注意ください。
- Q6. 解約はいつでもできますか?違約金はかかりますか?
- はい、マイページからいつでも解約手続きが可能です。最低利用期間の縛りや、解約に伴う違約金などは一切発生しませんので、安心して利用を開始できます。
まとめ
今回は、モバイル保険の特徴やメリット、補償範囲に加え、リアルな口コミ・評判についても解説してきました。再度、モバイル保険のメリットをおさらいしておきましょう。
- 月額700円で年間10万円まで補償可能
- 1契約で3台まで補償してくれる
- どこの修理店でも修理ができる
- Webサイトからすべての手続きを済ませることができる
このように、モバイル保険は加入メリットが多く、実際の加入ユーザーの口コミや評価も高いことが特徴です。年々、スマホの端末費用が高額になってきているからこそ、万が一のトラブルに備えてこの機会にぜひ加入しておくことをおススメします!